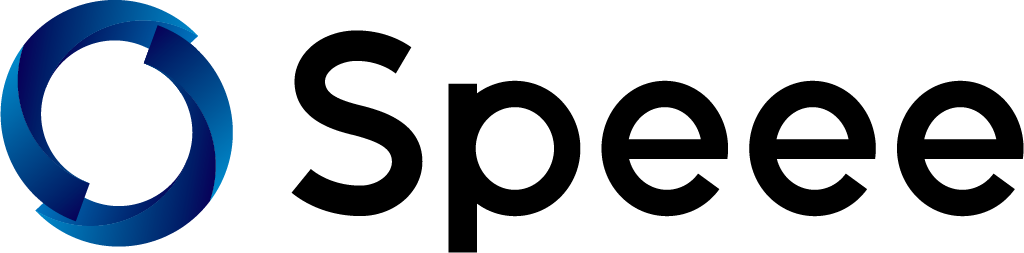屋根塗料の耐用年数は塗料の種類や家の環境、施工状況によっても変わってきますが、一般的には10~15年とされています。
耐用年数は目安であるため、適切に暮らしを守るためにも状況をきちんと把握することが大切です。
本記事では、塗料ごとの耐用年数の違いから、耐用年数を長持ちさせる方法についてまでを解説しています。ぜひ、参考にしてみてください。
 |
監修者:外装劣化診断士 小林 成光
600件以上の現地調査を実施する過程で得た専門性を生かし、日本発のネット見積もりシステムでビジネスモデル特許を取得。ヌリカエにて、外装工事の専門家として、顧客・加盟企業のサポート・コラムの監修に従事。
▼略歴・プロフィール |
屋根塗料の耐用年数はどのぐらい?
屋根塗料の耐用年数は一般的に10~15年程度が目安になります。
なお、新築後の塗り替えについては概ね10年を目安にするとよいとされています。
屋根塗料における耐用年数とは
屋根塗料における耐用年数とは、屋根塗料が適切な効果を発揮する期間のことです。
具体期には塗料を塗り、塗膜が劣化する前までの期間を指します。
塗料の種類によって耐用年数は異なるため、使用する塗料の目安となる耐用年数を把握しておくことが大切です。
塗料の種類ごとの耐用年数の違い

屋根塗料にはさまざまな種類があり、それぞれの塗料の種類ごとの耐用年数は以下の表の通りです。
<塗料の種類別耐用年数>
| 塗料名 | 耐用年数 |
|---|---|
| アクリル塗料 | 約5年~7年 |
| ウレタン塗料 | 約8年~10年 |
| シリコン塗料 | 約10年~13年 |
| フッ素塗料 | 約15年~20年 |
| ラジカル塗料 | 約12年~16年 |
| 無機塗料 | 約20年~ |
屋根塗料として一般に広く普及しているのが、シリコン塗料です。シリコン塗料の耐用年数は約10年~15年とされており、屋根塗料の耐用年数の基準となっています。
フッ素塗料の耐用年数は約15年~20年、無機塗料は約20年以上の耐用年数を誇っており、最も長い期間の利用が見込めます。
屋根塗装をする際には、耐用年数だけでなく費用も考慮して選ぶと後悔しないでしょう。
>>アクリル塗料の特徴とは?他塗料と比較したメリットデメリット
>>ウレタン塗装とは?メリット・デメリットや施工費用、製品の種類について解説!
>>シリコン塗料とは?特徴や価格、代表的な商品を紹介!
>>フッ素塗料の特徴、費用対効果は? 高価でも「屋根」と「雨どい」にはフッ素が効く!
>>ラジカル塗料とは?シリコン塗料との違いやメリット・デメリット、製品・単価を解説!
>>無機塗料って何?よくあるトラブルやおすすめのメーカーを紹介
屋根塗料の耐用年数が過ぎると起こる症状

屋根塗料の耐用年数が過ぎてしまうと、塗膜のひび割れやチョーキング(白化)など劣化症状が起こる可能性が高まります。
さらに、ひび割れやチョーキング(白化)に加えて以下のような症状も起こりえます。
チョーキング(白化)
色あせ、つや引け
こけ、藻の発生
金属部分のさびや腐食
塗膜にひび割れ・剥がれ
塗膜とは、屋根に塗布した塗料が時間の経過とともに乾燥し、形成される膜のことです。
雨や風などの影響によって、塗膜は徐々に耐久性をなくし、ひび割れや剝がれるなどの症状につながります。ひび割れや剥がれが発生している場合は、塗膜の保護機能が低下しているサインです。放置しておくと雨漏りの原因にもなり、建物内部の劣化にも起因してしまうため、早急な対応が求められます。
チョーキング(白化)
チョーキング(白化)は該当部分に触ると白い粉の様なものが付く状態です。
すでに塗膜の寿命がきているサインになるため、すぐに対応するようにしましょう
色あせ、つや引け
紫外線を浴び続けることが原因で、塗膜の表面が色あせている症状のことです。
建物の美観を損なうだけでなく、撥水性がなくなっているため屋根材に雨水が浸み込みやすくなるため、雨漏れなどの危険性が高まります。こけや藻の発生
色褪せが進行すると防水性も低下するため、水分を余分に吸収してしまい、こけや藻が発生しやすくなります。
放置してしまうと、屋根の劣化がより一層進行し、野地板と呼ばれる屋根の下地材が腐食する原因にもなるため、早急に対応してください。金属部分のさびや腐食
屋根の金属製の付属部材のさびや腐食の進行する可能性が高くなります。
放置してしまうと雨漏りの原因となり、日常生活に支障が出てきてしまいます。
屋根塗料の耐用年数を長持ちさせるには?

屋根塗料の耐用年数を長持ちさせるためには、以下の4つが大切です。
とくに定期的な塗装状態の確認は、劣化症状が見つかった際の迅速な塗り替えにつながるため、意識して行ってみてください。適切な塗料を選ぶ
機能性のある塗料を使う
信頼できる業者に依頼する
定期的に塗装状態を確認する
屋根の状態を良好に保つためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。
ひび割れや剥がれ・ズレなどを放置すると、雨漏りなどの被害につながります。定期的に塗装状態を確認し、劣化症状がみられた場合は早めに塗り替えを行うことが大切です。
とはいえ、屋根に登り塗装状態を確認することは危険を伴います。新築・前回塗装から10年経過したタイミングで、業者による定期点検を行うことがお勧めです。
適切な塗料を選ぶ
屋根塗装の耐用年数は塗料によって変わるため、耐候性に優れた塗料を適切に選ぶことも耐用年数を長持ちさせるためには重要です。
たとえばアクリル・ウレタン系の塗料を用いると初期費用は抑えられますが、ランニングコストが高額になってしまう場合があります。
塗料を選ぶ際は初期費用だけではなく、耐用年数から計算したランニングコストも意識して適切な塗料を選ぶようにしましょう。機能性のある塗料を使う
UVカット効果・遮熱効果など機能性の高い塗料を選ぶことも耐用年数を長持ちさせることにつながります。UVカット効果は、紫外線による色褪せを防ぎ、屋根の美しさを長持ちさせる効果をもち、遮熱効果は、屋根の表面温度を下げ、熱による劣化を防ぎます。
こうした機能性のある塗料かどうかも事前に確認しておくとよいでしょう。
信頼できる業者に依頼する
信頼できる業者に依頼することも屋根塗料を長持ちさせるためには重要です。
なぜなら専門業者は建物の状態や気象条件を考慮し、適切な塗料の選定と施工方法を提案できるからです。さらに塗装技能士などの資格を持つ職人が均一で適切な厚さの塗装を行うことで、より耐久性が向上が期待できます。施工後はアフターフォローや定期メンテナンスのサポートも行ってくれるため、早期の劣化を防ぎ、屋根塗料の寿命を延ばすことにつながります。
信頼できる業者を選ぶためには、複数社で相見積もりを取り、提案内容を確認することが大切です。
屋根材による耐用年数の違いと特徴
| 塗料名 |
スレート屋根 |
ガルバリウム屋根 | 瓦屋根 |
|---|---|---|---|
| 耐用年数 | 8〜15年 | 10〜25年 | 10〜30年 |
| 費用(1㎡あたり) | 5,000〜8,000円/㎡ | 6,500〜9,000円/㎡ | 8,000〜12,000/㎡ |
| コスパ比較(単価÷耐用年数) | 1,000円/㎡ | 900円/㎡ | 1,200円/㎡ |
屋根塗装の耐用年数は、種類によって大きく異なります。
一般的に、屋根材の耐用年数は8〜15年程度とされていますが、定期的なメンテナンスを行うことで寿命を延ばすことが可能です。
主な屋根材ごとの耐用年数の違いと特徴は以下の通りです。。
スレート屋根

| 耐用年数 | 8〜15年 |
|---|
スレート屋根の塗装耐用年数は、8〜15年程度です。
スレートは比較的安価で軽量な屋根材ですが、経年劣化により表面が粉状になる「チョーキング」が起こりやすい特徴があります。
塗装を行う際は、下地処理を丁寧に行い、適切な塗料を選択することが重要です。高品質なシリコン系やフッ素系の塗料を使用することで、耐久性を向上させることができます。
ガルバリウム屋根

| 耐用年数 | 10〜25年 |
|---|
ガルバリウム屋根の塗装耐用年数は、10〜25年程度とされています。ガルバリウム鋼板は耐久性に優れた屋根材で、適切なメンテナンスを行えば長期間の使用が可能です。
ガルバリウム屋根は元々耐久性が高いため、新築時から10年以上は塗装の必要がない場合もあります。
ただし、経年劣化による色あせや光沢の低下が見られた場合は、塗装を検討する必要があります。
瓦屋根

| 耐用年数 | 10〜30年 |
|---|
瓦屋根の塗装耐用年数は、セメント瓦の場合は10〜20年、粘土瓦の場合は30年以上とされています。
瓦屋根では、定期的な点検とメンテナンスが重要です。瓦のズレや割れ、漏水などの問題が発生していると劣化症状が早まってしまうためです。
問題が発生した場合は、必要に応じて補修や塗装を行います。
とくにセメント瓦は経年劣化により表面が劣化しやすいため、適切な時期に塗装を行うことが求められます。
まとめ
雨風から建物を守る屋根を長持ちさせるためには、定期的に塗装状態を確認することが不可欠です。
確認時に劣化症状が見られた際には放置せず、早めの塗り替えを行うことを意識しましょう。
本記事のポイントをまとめると、以下のようになります。
- 定期的な点検で屋根の劣化のサインを見逃さない
- 塗料の耐用年数とは、塗布した塗料の効果や効能が発揮されている期間
- 屋根塗料は、ランニングコストを意識して選定する
屋根のメンテナンスを効果的に実施するためには、不具合が生じる前に塗り替えを行うことが大切です。
塗り替えの際は塗料の耐用年数とコストのバランスを考えて、長期的な視点から選ぶようにしましょう。
塗料の特徴を正しく理解することで、満足度の高い屋根塗装につながります。