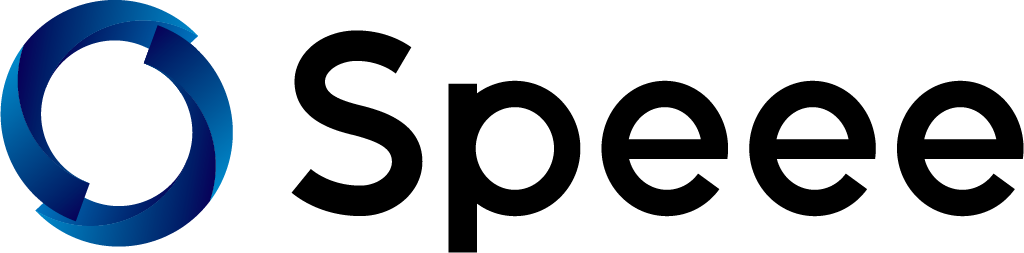外壁や屋根材を何にするか検討されるなかで「ガルバリウム鋼板」という建材が良く出てきますが「ガルバリウム」とはどのような材質なのでしょうか。
そこで本記事では、ガルバリウムとはどのような素材なのかについて詳しく解説します。
加えて、ガルバリウム鋼板のデメリットとメリット、窯業系サイディングとの比較や施工例についてもご紹介していますので、ご自宅の外壁や屋根の建材を考えている方の参考となれば幸いです。
600件以上の現地調査を実施する過程で得た専門性を生かし、日本発のネット見積もりシステムでビジネスモデル特許を取得。ヌリカエにて、外装工事の専門家として、顧客・加盟企業のサポート・コラムの監修に従事。
▼略歴・プロフィール ガルバリウムとは、一般的に「ガルバリウム鋼板」と呼ばれる金属製の建材のことを指します。主に住宅の外壁や屋根に使われる人気の素材です。 このガルバリウム鋼板は、1972年にアメリカで開発されました。日本では1980年代頃から使われるようになり、その優れた耐久性と、金属ならではのシャープでおしゃれな見た目から、多くの住宅で採用されています。 ガルバリウムは、鉄の板を、アルミニウムと亜鉛、シリコンでめっきしたものになります。アルミニウムと亜鉛の長所である、サビにくさと耐熱性をもつ優れた金属です。 ガルバリウムのメリットとデメリットを以下にまとめました。 各メリットとデメリットについて、詳しく解説します。 ガルバリウムは、めっき層に使用されている「亜鉛」「アルミニウム」「ケイ素」の働きにより、金属素材でありながら錆びに強いのが特徴です。 同じ金属素材のトタンの耐用年数は10年前後ですが、ガルバリウムの耐用年数は最大30年と、3倍ほど耐久性が高くなっています。 また、他の金属製の外壁材や屋根材と比較すると価格が比較的安い点も魅力メリットです。他の金属系建材の約「2分の1~3分の1」程度となります。 耐久性が高くメンテナンスの手間が少ないことも含めると、コストパフォーマンスに優れた素材と言えるでしょう。金属ならではのシャープでモダンなデザイン性の高さも人気の理由です。 金属素材であるガルバリウムは熱を通しやすいため表面温度が高くなりやすく、室内が暑くなる原因となります。 ただし、現在では断熱材一体型ガルバリウム鋼板が使用されるため、室内の温度についてそこまで心配される必要はないでしょう。 また、屋根材として使用する場合は雨音が響きやすいというデメリットもあります。2階部分にいるときや小屋の屋根に使う場合は、特に雨音が気になってしまう可能性もあるでしょう。 これらの熱や音の問題への対策が施されたガルバリウム鋼板も存在しますが、一般に紹介されるガルバリウム鋼板の価格よりも高くなるため注意してください。 ガルバリウム鋼板と並んでよく検討されるのが窯業系サイディングです。 特に外壁材ではガルバリウム鋼板と人気を二分している窯業系サイディングですが、それぞれ性能や価格などが大きく違います。 ガルバリウム鋼板と窯業系サイディングのメリットとデメリット、価格、耐用年数などの比較をまとめました。 データ出典:「ヌリカエ」が行った2025年5月のデスクリサーチより
それぞれの項目について詳しく解説します。 ガルバリウム鋼板は金属素材ながらサビに強く、比較的安価でシャープな外観が魅力です。一方で、夏の暑さが伝わりやすく雨音も響きやすいため、断熱材や遮音対策が必要な場合があります。断熱材一体型のガルバリウム鋼板は、通常のものと比べて施工費用が高くなりますのでご注意ください。 窯業系サイディングは、耐火性が高く、デザインも豊富なのが特徴です。ただし、重くて蓄熱性がありガルバリウム鋼板よりも汚れが付きやすいため、メンテナンスコストがかかります。 どちらも一長一短があるため、立地や予算、性能に応じて選ぶことが大切です。 ガルバリウム鋼板の相場は1㎡あたり約3,000円~4,000円、窯業系サイディングは4,000円~6,000円/㎡が相場となります。 窯業系サイディングの方がガルバリウム鋼板よりも高めです。広い面積をリフォームする場合、1㎡あたりの差が総額に大きく影響するため、初期費用を重視する方はガルバリウム鋼板の方が価格を抑えらえるでしょう。 ガルバリウム鋼板の耐用年数はおよそ20年~35年とされており、しっかりと施工・メンテナンスすれば長期間使えます。 一方、窯業系サイディングは30年~40年と、素材自体の寿命はやや長めです。ただし、窯業系サイディングは塗装やコーキングの補修など、ガルバリウム鋼板よりも定期的なメンテナンスが必要となります。 外壁や屋根は長期間家を守るものであるため、数十年単位でのメンテナンスコストも考えることをおすすめしまs。 窯業系サイディングはノーマルなフラットな見た目のものから、レンガ調や石積調、タイルや木目調など様々多彩な柄やカラーのなかから選ぶことができます。 ガルバリウム鋼板は、鉄素材ならではのシンプルで直線的な印象が強く現代的で無機質なスタイルとなります。選べるデザインのバリエーションは窯業系サイディングより少ない点に注意してください。 それぞれのデザイン幅がかなり違うため、理想とする外観やイメージを固めておくと良いでしょう。 ガルバリウム鋼板には様々なデザインがあります。 ここでは外壁・屋根の色として人気の高い「ブラック系」「グレー系」「ホワイト系」「ブルー系」「グリーン系」の3色ごとのデザイン比較をご紹介しますので、ご自宅を外壁や屋根の建材を検討する際の参考になれば幸いです。 【事例①】 =45″ target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”]画像出典:アイジー工業
黒いガルバリウム鋼板で外壁を統一させた事例です。黒に統一することで重厚感が全面に出ており、植栽や木材とのコントラストが最も生える色となります。 また、最も汚れが目立ちにくい色となるため、多少の汚れや傷でも美観を保ちやすい点がメリットです。 【事例②】 黒いガルバリウム鋼板で屋根を葺いた事例です。グレー系と並んで選ばれることの多い色となります。 「屋根を黒くすると室内が厚くなるのでは?」と心配される方もいますが、多少の差はあれど黒にしたらかといって極端に室内が熱くなるくなるということはありません。 塗料には遮熱塗料という、太陽光の熱を反射して屋根の表面温度を抑えるものもありますので、心配な方は検討してみるとよいでしょう。 【事例①】 グレーのガルバリウム鋼板で外壁を統一させた事例です。黒ほど重たい印象になりづらいため、シックな印象を残しつつ温かみのある雰囲気を出すことができます。

監修者:外装劣化診断士 小林 成光
「監修者|小林 成光(株式会社Speee)」ガルバリウムとは?

ガルバリウムのメリット・デメリット比較
メリット
デメリット
・錆びに強い
・金属素材としては安価
シャープな質感でデザイン性が高い・夏場に屋内が暑くなる
・雨音が大きい
・欠点を補うと価格が高くなるガルバリウムのメリット
メリット
・錆びに強い
・金属素材としては安価
・シャープな質感でデザイン性が高いガルバリウムのデメリット
デメリット
・夏場に屋内が暑くなる
・雨音が大きい
・欠点を補うと価格が高くなるガルバリウム鋼板と窯業系サイディングの比較
写真
メリット
デメリット
価格
耐用年数
デザイン性
ガルバリウム鋼板

・錆びに強い
・金属素材としては安価
・シャープな質感でデザイン性が高い・夏場に屋内が暑くなる
・雨音が大きい
・欠点を補うと価格が高くなる3,000円~4,000円/㎡
20年~35年程度
窯業系サイディングより少ない
窯業系サイディング

・耐用年数が長い
・耐火性が高い
・デザインが豊富・メンテナンスコストがかかる
・蓄熱性がある
・素材そのものが重い4,000円~6,000円/㎡
30年~40年程度
様々なバリエーションあり
メリット・デメリットの比較
ガルバリウム鋼板
窯業系サイディング
メリット
・錆びに強い
・金属素材としては安価
・シャープな質感でデザイン性が高い耐用年数が長い
耐火性が高い
デザインが豊富
デメリット
・夏場に屋内が暑くなる
・雨音が大きい
・欠点を補うと価格が高くなるメンテナンスコストがかかる
蓄熱性がある
素材そのものが重い価格の比較
ガルバリウム鋼板
窯業系サイディング
3,000円~4,000円/㎡
4,000円~6,000円/㎡
耐用年数の比較
ガルバリウム鋼板
窯業系サイディング
20年~35年程度
30年~40年程度
デザイン性の比較
ガルバリウム鋼板
窯業系サイディング
窯業系サイディングより少ない
様々なバリエーションあり
ガルバリウム鋼板の色別デザイン比較
色
外壁
屋根
ブラック系


グレー系


ホワイト系


ブルー系


グリーン系


ブラック系ガルバリウムのデザイン例


グレー系ガルバリウムのデザイン例

【事例②】

こちらは、グレーのガルバリウム鋼板で屋根を葺いた事例になります。グレーは屋根の色として広く採用されるものです。
一口にグレーといっても濃淡や質感は様々でラインナップも豊富なので、イメージに合わせて様々な選択肢のなかから選ぶことができます。
事例の詳細については、ぜひ事例のページをご覧ください
ホワイト系ガルバリウムのデザイン例
【事例①】

外壁を白いガルバリウム鋼板で統一した施工事例です。ガルバリウム鋼板は金属素材のためグレーなどの濃色が多いですが、このような白いものもラインナップされています。
白は光を反射するため、金属特有の光沢や冷たい質感が出にくくなります。そのため、ガルバリウム鋼板特有のデザインが気になる方でも選びやすい色といえるでしょう。
【事例②】

こちらは、屋根を白いガルバリウム鋼板で葺いた事例になります。一般的に屋根を白い色にすることは珍しいですが、商品としてラインナップされているため施工自体は可能です。
白は太陽光の吸収率が黒に比べて低いため、素材そのものが痛みにくくなるというメリットがあります。ただし、屋根・外壁材は色によって性能に大きな差が出ることはありません。
ブルー系ガルバリウムのデザイン例
【事例①】

外壁をネイビーブルーのガルバリウム鋼板で統一した施工事例です。ブルー系はブラウン系の色との相性も良く、こちらの事例ではドアやポストとのコントラストが映えおしゃれな印象にまとまっています。
暗めのブルー系色は周囲との調和を図りながら個性を出しやすい色のため、ガルバリウム鋼板でも選ばれることの多いカラーです。
【事例②】

こちらの事例は、屋根にブルー系のガルバリウム鋼板を葺いた事例になります。屋根のため普段は目立たない箇所になりますが、外壁の色を合わせることで洗練された印象やシャープな印象を出すことができるでしょう。
ネイビーブルーなど濃色の場合は、ホワイト系などの明色に比べて熱の吸収率が高くなります。そのため屋根材の劣化スピードが熱により早まる可能性に注意してください。
グリーン系ガルバリウムのデザイン例
【事例①】

こちらは、外壁をディープグリーンのガルバリウム鋼板を張った施工事例です。ブルー系と同様、緑と相性がよく共にアースカラーであるブラウンがアクセントになり柔らかいながらも存在感のある印象になっています。
グリーン系のガルバリウム鋼板もよく使われる外壁材の一つです。ただし、色が暗くなるほど細かい擦り傷などが目立ちやすくなるため注意してください。
【事例②】

こちらは、駅舎の屋根をモスグリーンの色味をもつガルバリウム鋼板で葺いた事例になります。外壁のダークブランと相まって、落ち着きがあり重厚感のある印象に仕上がっています。
ブラック系やブルー系と同じく、濃色の場合は太陽光の熱吸収率が高くなるため建材の劣化スピードが早まる可能性が高いです。遮熱塗料や熱の伝わりを抑制する工夫をするとよいでしょう。
【状況別】ガルバリウム鋼板のメンテナンス方法
ガルバリウム鋼板は、年数や劣化状態によって適切なメンテナンスが異なります。
- 10年未満で目立った劣化なし:洗浄
- 15年前後で軽微な劣化がある:塗装
- 穴や下地の劣化がある:張り替え・重ね張り
各状況とメンテナンス方法についてそれぞれ詳しく解説します。
10年未満で目立った劣化なし:洗浄
ガルバリウム鋼板は耐久性に優れているため、10年未満であれば目立った劣化は少ないことが一般的です。しかし、表面にはホコリや汚れが付着しやすいため、長持ちさせるには定期的な洗浄がおすすめです。
洗浄は中性洗剤と柔らかいブラシやスポンジを使って優しく行いましょう。高圧洗浄機を使う場合は、圧力を調整して表面を傷つけないように注意が必要です。
15年前後で軽微な劣化がある:塗装
築15年程度になると、ガルバリウム鋼板の表面に色あせや小さな傷が見られることがあります。これらの軽微な劣化は、塗装によるメンテナンスがおすすめです。
塗装前には、表面の汚れやサビをしっかりと除去し下地処理を丁寧に行います。塗料には防サビ剤を配合したクリヤータイプのものもあるので、ガルバリウム鋼板のデザインを消さないように塗装することも可能です。
塗装は専門業者に依頼するようにしましょう。プロによる提案と施工によって高い仕上がりに期待にきます。
穴や下地の劣化がある:張り替え・重ね張り
ガルバリウム鋼板に穴が開いたり下地材が劣化している場合は、塗装や部分的な補修での対応は難しくなります。そのため、外壁自体を新しくする張り替えや重ね張りが必要です。
張り替えは既存の外壁材を撤去し、新しいものに交換する方法です。下地の状態も確認・修復できるため、外壁全体の劣化が激しい場合は張り替えが適しています。 重ね張りは、既存の外壁材の上から新しい外壁材を重ねる方法です。張り替えよりも費用が抑えられますが、耐震性が弱まる、外壁内部の劣化は直せない点に注意してください。どちらが適しているかは専門業者による点検が必要となります。
ガルバリウムはこんな人におすすめ
メリット・デメリットの両面をふまえて、ガルバリウムを使った家は以下に当てはまる人には向くと判断できます。
- 「耐震性」を重視する人
- 「カバー工法」を希望する人
- 今の家に「30年以上」住む予定の人
- 金属の「モダンなデザイン」が好みの人
ガルバリウムは、外壁・屋根材のなかで最も軽いため、耐震性を気にされる方におすすめとなります。
また、メタリックでシャープな外見の家が好みであれば、ガルバリウム鋼板が良いでしょう。窯業系サイディングでは金属の質感を出すことは困難であるためです。
以上、本記事の解説がリフォームのお役に立ちましたら幸いです。