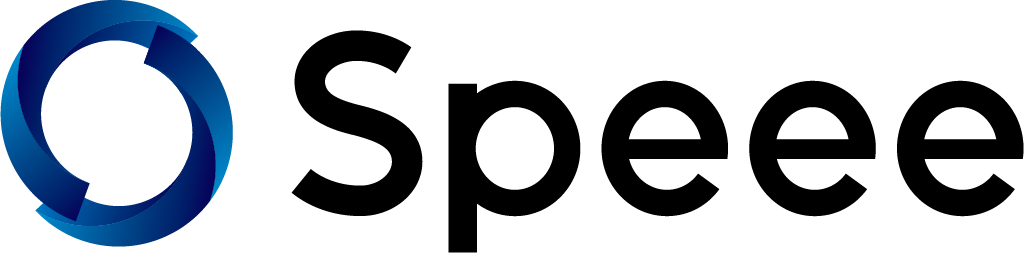屋根の耐用年数は何年?屋根材ごとの寿命やメンテナンス方法も解説!



あなたのお家
外壁塗装するといくら?
屋根の耐用年数は、20年~30年が一般的です。しかし屋根材によっては大きく異なり、40年以上持つ場合もあります。
耐用年数を最大限に延ばすためには定期的なメンテナンスが欠かせません。
そこでこの記事では、屋根材ごとの耐用年数・メンテナンス周期を詳しく解説します。
屋根材ごとの耐用年数・メンテナンス周期をまとめると、以下の通りです。
| 屋根材 | 耐用年数(寿命) | メンテナンス周期 |
|---|---|---|
| スレート屋根 | 30年 | 5年 |
| ガルバリウム鋼板 | 30~40年 | 15年 |
| トタン屋根 | 20~30年 | 10年 |
| 和瓦(釉薬瓦) | 30~40年 | 15年 |
| アスファルトシングル | 30~40年 | 5年 |
| セメント瓦 | 30年 | 10年 |
また、メンテナンスするべきサインと費用相場についても解説するので、「自宅って工事するべきなの?」と考えている方はぜひ参考にしてください。
この記事を監修しました

株式会社Speee
小林 成光
所有資格
外壁アドバイザー、外装劣化診断士、ホームインスペクター
専門分野
外壁工事
職業
外壁アドバイザー、外装劣化診断士、ホームインスペクター
600件以上の現地調査を実施する過程で得た専門性を生かし、日本発のネット見積もりシステムでビジネスモデル特許を取得。ヌリカエにて、外装工事の専門家として、顧客・加盟企業のサポート・コラムの監修に従事。
屋根の耐用年数とは?屋根材ごとの耐用年数の一覧表
| 屋根材 | 耐用年数(寿命) | メンテナンス周期 | メンテナンスのサイン | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|---|---|
| スレート屋根 | 30年 | 5年 | カビ・コケの発生、退色、割れ、釘のゆるみが見られたら「塗装」や「葺き替え」を検討。 | 軽量で耐震性が高く、費用も比較的安価 | 薄く割れやすいため、こまめなメンテナンスが不可欠 |
| ガルバリウム鋼板 | 30~40年 | 15年 | 錆び、穴空き、釘のゆるみがあれば「塗り替え」または「葺き替え」が必要。 | 軽量で耐震性に優れ、サビにも強い | 断熱性低く、デザインのバリエーションも少ない |
| トタン屋根 | 20~30年 | 10年 | 錆びや穴空きが進行している場合、「塗り替え」や「葺き替え」を実施。 | 施工が比較的容易で、耐震性が高い | 耐久性や断熱性、遮音性は低い |
| 和瓦(釉薬瓦) | 30~40年 | 15年 | 瓦のずれや破損、棟瓦のゆるみが見られたら「締め直し」や「葺き替え」を検討。 | 和風建築に合う美しいデザイン | 重量があり、建物への負担が大きい |
| セメント瓦 | 30年 | 10年 | カビ・コケ・色あせ、瓦のずれや破損が進行していれば「塗装」や「葺き替え」を検討。 | 日本瓦よりも安価で施工できる | 耐久性や耐震性は劣っている |
| アスファルトシングル | 30~40年 | 5年 | 剥がれ、浮き、藻やコケの広がりがある場合は「再接着」や「葺き替え」が適切。 | 軽量で防水性や吸音性に優れている | 強風で剥がれる可能性があり、勾配が緩い屋根は不向き |
「屋根の耐用年数」と、「初回のメンテナンス時期をむかえる年数」を、屋根材別にまとめたものが上記の表です。それぞれの耐用年数の根拠と、築年数ごとに必要なメンテナンスは、各屋根材の章をご覧ください。
屋根には「日光の遮断」「風の遮断」「建物の印象決め」などさまざまな役割がありますが、その中でももっとも重要な役割は「雨の遮断」、つまりは『防水性』ではないでしょうか。
住宅のトラブルのなかでも、雨漏りの影響は大きいものです。家が雨漏りが起こすと、内装・家財・住人が水濡れの被害を受けるばかりでなく、建物そのものの老朽化が早まり、その家に住める年数が大幅に短くなってしまいます。
そこで本記事では、住宅の耐用年数を「防水性を保っていられる年数」と定義して解説しています。
「スレート屋根」の耐用年数│30年

スレート屋根はセメントを主成分とした薄い板を加工した屋根材で、フラットな形状であることが特徴です。
「カラーベスト」「コロニアル」など、さまざまな呼ばれ方をしておりますが、いずれもスレート屋根のことを指しています。
スレート屋根の耐用年数は30年前後が目安です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 耐用年数 | 約30年 |
| メンテナンス時期 | 築5年ごと |
| メンテナンス内容 | 業者によるヒビ割れの点検・補修を定期的に行う。 |
スレート屋根についてもっと詳しく知りたい方はこちら

「ガルバリウム鋼板屋根」の耐用年数│30年~40年

ガルバリウム鋼板はアルミニウムと亜鉛を主成分とした金属板の一種のことで、耐久性や軽量性に優れた外壁材です。
ガルバリウム鋼板の耐用年数・寿命は、30~40年が目安となっており、錆びにも比較的強い金属なので、ほとんどの場合30年以上は使い続けられるでしょう。
なお、ガルバリウム鋼板の寿命よりも、内部のルーフィングの寿命のほうが早く訪れる可能性が高く、気を配る必要があります。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 耐用年数 | 約30~40年 |
| メンテナンス時期 | 築15年目 |
| メンテナンス内容 | 棟板金を固定するクギが弱くなるため、棟板金と下地木材の交換を行う。 |
ガルバリウム鋼板についてもっと詳しく知りたい方はこちら
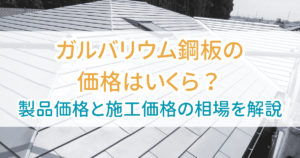
「トタン屋根」の耐用年数│20年~30年

トタン屋根とは、「トタン」と呼ばれる薄い鉄板に亜鉛メッキを施した板状の資材を活用した屋根材のことで、住宅から倉庫、工場にも利用されています。
耐震性の高さが魅力ですが、昨今ではより耐久性が高い屋根材が登場したことで、利用される機会は減少しています。
トタン屋根の耐用年数・寿命は、20~30年が目安です。錆びの量によっては、20年前後しか保たないことも少なくありません。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 耐用年数 | 約20~30年 |
| メンテナンス時期 | 築10年目 |
| メンテナンス内容 | 錆びが進みやすいため、錆びの除去と防水性を回復する塗装を実施。 |
ガルバリウム鋼板についてもっと詳しく知りたい方はこちら

「和瓦(釉薬瓦)屋根」の耐用年数│30年~40年以上

和瓦(釉薬瓦)は、粘土やセメントを焼き固めて作られている屋根材で断熱性や遮音性に優れたメリットがあります。
陶器とおなじ製法で作られており、屋根材そのものの寿命は50年以上あります。しかし重要なのは、ルーフィングの寿命もっと早く訪れることです。
そのため、屋根の耐用年数・寿命もルーフィングに合わせた30~40年が目安となります。
ただし和瓦屋根の場合は、[text style=”15″ extra-class=”u-txt–strong”]ルーフィングだけを交換して屋根材は同じものを使い続ける「葺き直し」というメンテナンスが可能[/text]なのがポイントです。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 耐用年数 | 約30~40年 |
| メンテナンス時期 | 築15年目 |
| メンテナンス内容 | 棟瓦の土台が劣化するため、棟の取り直しを行う。 |
「セメント瓦屋根」の耐用年数│30年

瓦屋根の耐用年数は30年前後が目安です。
セメント瓦は、和瓦とは違い塗膜に寿命があるため塗装メンテナンスが必要なのが特徴です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 耐用年数 | 約30年 |
| メンテナンス時期 | 築10年目 |
| メンテナンス内容 | 塗膜が劣化するため、瓦の防水性を回復させる塗装を行う。 |
瓦屋根についてもっと詳しく知りたい方はこちら

「アスファルトシングル屋根」の耐用年数

アスファルトシングルとは、表面にアスファルトや繊維でできたシートを接着剤と釘で屋根の表面に固定して使う外装材です。
防水性に優れ、施工費用も安価な一方で、安心して使うにはこまめに点検して剥がれを点検・補修する必要があります。
アスファルトシングル屋根の耐用年数は30~40年が目安です。ただし、メンテナンスを全くしないと20年前後で寿命がきてしまいます。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 耐用年数 | 約30~40年 |
| メンテナンス時期 | 築5年ごと |
| メンテナンス内容 | 剥がれの点検と補修を実施。5年目、10年目、15年目と継続する。 |
アスファルトシングルについてもっと詳しく知りたい方はこちら

下地・防水シートやそのほか屋根に関わる耐用年数
下地の耐用年数│30~40年
屋根の耐久性を考える際、屋根材の寿命だけでなく、屋根の下地の寿命にも注目したほうがよいでしょう。なぜなら、屋根の下地が耐用年数を過ぎて劣化が進んでしまうと、建物全体に影響が及ぶからです。
屋根の下地は、以下の要素で構成されています。
- 野地板(のじいた):屋根材を支える木製の板
- 防水シート(ルーフィング):雨水の侵入を防ぐ防水シート
- 垂木(たるき):屋根の骨組みとなる構造材
それぞれの耐用年数は以下の通りです。
- 防水シート(ルーフィング):30年
→ 一般的なアスファルトルーフィングは15~20年、高耐久ルーフィングは30年以上持つものも。 - 野地板:30~40年
→ 合板の場合は劣化が早く、20~30年で交換が必要なことが多い。 - 垂木:40年以上
→ 木材の状態によるが、湿気やシロアリ被害があると寿命が短くなる。
屋根の下地の中でも特に重要なのが、防水シート(ルーフィング)です。そのため、防水シートについてはこの後詳しく解説します。
防水シートの耐用年数│30年
屋根の防水能力には、表面の「屋根材」だけでなく、屋根の下地に張り付けられている防水シート(ルーフィング)も大きく関わっています。
防水シートとは、屋根材と、屋根の下地木材の間に張られている防水機能をもったシートです。内部を通ってきた水分が下地木材に触れるのを防ぎ、勾配を利用して屋根材のすき間や軒先から排出する役割をもっています。

防水シート重要性は意外にも大きく、防水シートさえ無事であれば、屋根材に劣化があっても建物は雨漏りを起こしません。そのため、[text style=”15″ extra-class=”u-txt–strong”]屋根の耐用年数を気にする場合は、屋根材の寿命だけではなく、防水シートの寿命も気にする[/text]必要があります。
防水シートの耐用年数・寿命は、30年が目安です。
「防水シート」について詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。
>>「ルーフィングシートとは?種類ごとにメリット・デメリットを解説」
雨樋の耐用年数│30~50年
雨樋(あまどい)は、屋根に降った雨水を集めて適切に排水する重要な役割を持っています。雨樋の耐用年数は、使用される素材によって異なります。
| 雨樋の素材 | 耐用年数の | 特徴 |
|---|---|---|
| 塩化ビニル(樹脂製) | 20~25年 | 軽量でコストが安いが、紫外線や温度変化に弱い |
| ガルバリウム鋼板 | 30~40年 | サビに強く、耐久性が高い |
| 銅製 | 50年以上 | 経年変化で味わいが増すが、高価 |
| アルミ製 | 30~50年 | 軽量でサビに強く、メンテナンスしやすい |
雨樋の劣化の原因は経年劣化に加えて、ごみや落ち葉のつまりによる排水不良もあります。落ち葉などが詰まったまま放置されて耐用年数が短くなるケースが多いので、定期的に点検するようにしましょう。
屋根の棟の耐用年数

棟とは、屋根の面と面が合わさる頂点の部分を指します。棟にはいくつかの種類があり、屋根の形状によって呼び方が異なります。
| 棟の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 大棟(おおむね) | 屋根の一番高い部分にある水平の棟 |
| 隅棟(すみむね) | 寄棟や入母屋屋根などで、屋根の隅から頂上へ伸びる棟 |
| 下り棟(くだりむね) | 大棟から軒先へ向かって伸びる棟 |
屋根の棟の耐用年数は、素材によって異なります。
- 瓦屋根の棟:20~30年(漆喰の補修は10~15年ごと)
- スレート・金属屋根の棟板金:15~20年
棟は他の屋根材よりも劣化しやすく、強風など気候の影響を受けやすかったり、地震の揺れで棟瓦がすれてしまうこともあります。
10年に1回ほど、棟瓦のひび割れ・浮きをチェックするとよいでしょう。
屋根の耐用年数を長くするためのメンテナンス
屋根は住宅の中でも特に厳しい環境にさらされる部分です。定期的なメンテナンスを行うことで、屋根の寿命を延ばし、家全体を守ることができます。特に、劣化のサインを早期に発見し適切な対応を取ることが重要です。
屋根のメンテナンス・工事の費用相場
屋根のメンテナンスや工事には費用がかかりますが、早めの対応が結果的にコスト削減につながります。以下は主な工事内容とその費用の目安です。
| 工事内容 | 費用相場 |
|---|---|
| 塗装 | 30万円〜50万円 |
| 部分修理(瓦の差し替えなど) | 5万円〜20万円 |
| 葺き替え | 100万円〜200万円 |
| カバー工法 | 80万円〜150万円 |
| 棟板金交換 | 15万円〜30万円 |
これらの費用は屋根材の種類や状態、建物の規模によって変動します。信頼できる業者に見積もりを依頼し、比較検討することをおすすめします。
「塗装」について詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。

まとめ
屋根の耐用年数は、屋根材ごとに異なります。また、屋根は適切なタイミングでメンテナンスをすることで、耐用年数をより伸ばすこともできます。
ですから、自宅の屋根の状態を適切に把握し、適切なタイミングでメンテナンスを行うことが重要です。しかし屋根は普段登って直接確認をすることが少ないので、自分では気が付けなくて、いつの間にか雨漏りしていた…となってしまうことが多いです。
ぜひご自宅の屋根の素材を確認し、「自宅は耐用年数を過ぎているかも!?」と思った方はプロに点検を依頼してみてください。
参考記事・ウェブサイト
菊池克弘『住宅リフォーム重要事項32選』都市環境建設 2015
建築工事研究会『積算資料ポケット版 住宅建築編 2021年度版』一般社団法人経済調査会 2020