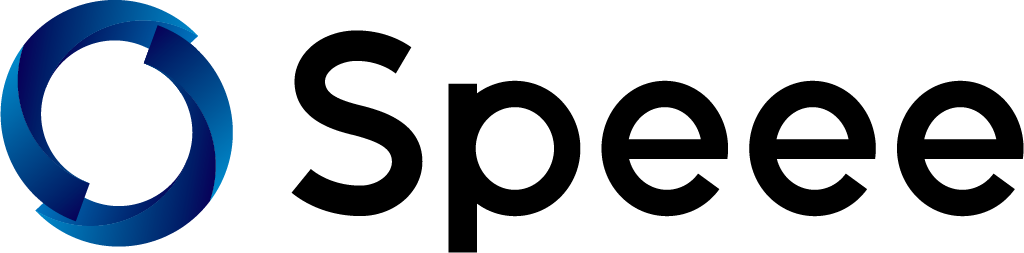|
監修者:宅建士・FP技能士 澤﨑 勝彦
宅地建物取引士(東京都登録)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士。
▼略歴・プロフィール |
リフォーム補助金は8種類
住宅のリフォームで受けられる補助金制度は以下の8種類があります。
- 【国】子育てエコホーム支援事業
- 【国】先進的窓リノベ2024事業
- 【国】給湯省エネ2024事業
- 【国】賃貸集合給湯省エネ2024事業
- 【国】長期優良住宅化推進事業
- 【国】断熱リフォーム支援事業
- 【自治体】各市区町村の補助金制度
- 【自治体】介護保険制度
次章から各補助金制度の支給条件や手続方法、注意点などを詳しく解説していきます。
①子育てエコホーム支援事業

「子育てエコホーム支援事業」は、住宅の所有者が自宅をリフォームしたり、子育て・若者夫婦世帯が一定の省エネ性を満たす新築住宅の取得を行った場合に費用の一部を補助するという制度です。
制度の重要ポイント
- 補助金額は最大30万円~60万円
- 「断熱改修」か「エコ住宅設備の設置」が必須
- 国の登録事業者にリフォームを依頼する必要あり
補助金額
「子育てエコホーム支援事業」を利用してリフォームをした場合に受け取れる上限金額は以下のとおりです。

支給上限額は通常30万円ですが、子育て世帯・若者夫婦世帯に当てはまる場合や、購入した中古住宅を一定期間内に増築する場合等に当てはまると、補助上限が最大60万円まで引き上げられます。
補助金の決まり方
子育てエコホーム支援事業では、70種類以上の工事に対して面積や建材の省エネ性能に応じて数千円から十数万円程度の金額が割り当てられています。
支給額は、そのうち自分が行う工事に応じた金額を合計したものとなります。
支給条件
「子育てエコホーム支援事業」で補助金を受け取るための条件は以下のとおりです。
- 「断熱改修」「エコ住宅設備の設置」を必ず行うこと
- 支給額が5万円以上となること
- リフォームは制度の登録事業者に発注すること
最大のポイントは、「断熱改修」か「エコ住宅設備の設置」のどちらかのリフォームは必須であることです。
具体的には、別途、窓・扉・天井・床・外装などの「断熱改修」か、太陽光発電システムやエコキュートなどの「エコ住宅設備の設置」が当てはまります。
| 種類 | 工事内容の例 |
|---|---|
| 開口部の断熱改修 | ガラス交換、内窓交換、外窓交換、ドア交換 |
| 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修 | 各部の全体断熱・部分断熱、床の基礎断熱 |
| エコ住宅設備の設置 | 太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽、高効率給湯器、節湯水栓、定置用蓄電池 |
また、必須工事以外では以下のようなリフォーム工事が補助対象ですが、これら単独では補助金は受け取れません。
上記の必須工事と同時に行った場合にのみ、補助金の支給対象となります。
| 種類 | 工事内容の例 |
|---|---|
| 子育て対応改修 | 対面キッチン化、窓・ドアの防犯性向上、騒音配慮など |
| 防災性向上改修 | 割れにくい窓ガラスへの交換など |
| バリアフリー改修 | 手すり設置、段差解消、廊下の拡張など |
| エアコンの設置 | 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置 |
| 瑕疵保険等への加入 | ― |
申請手順
本制度の申請は、認定を受けた登録事業者(工事業者)が行います。
そのため、施主側(リフォーム発注者)は手続きする必要はありません。そのため申請をスムーズに進めてくれるリフォーム会社を選ぶことが大切になります。
公式サイトから補助金利用を相談できる事業者の検索が行なえます。
■問い合わせ窓口
・窓口:子育てエコホーム支援事業事務局
・電話番号:0570-0550-224(ナビダイヤル)、03-6625-2874
※受付時間 9:00~17:00(土日祝含む)
・公式サイト:住宅省エネ2024キャンペーン 補助事業合同お問い合わせ窓口
現在の募集状況(2024/03/06更新)
本制度は受付開始前です。交付申請期間は2024年3月中下旬 ~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)となっています。
最新の情報は、子育てエコホーム支援事業の公式サイトをご確認ください。
②先進的窓リノベ2024事業

「先進的窓リノベ2024事業」とは、住宅の窓の断熱性を高めるリフォームを行った場合に補助金が受け取れる制度です。
制度の重要ポイント
- 支給額はリフォームする窓のタイプや数によって決定
- 補助金額は窓1箇所あたり5,000円~266,000円。最大で200万円
- 事業の登録事業者を利用した場合のみ利用可
補助金額
「先進的窓リノベ2024事業」の補助金額は以下のとおりです。
- ガラス交換:1枚5,000円~55,000円
- 内窓設置:1箇所23,000円~112,000円
- 外窓交換(カバー工法):1箇所43,000円~266,000円
- 外窓交換(はつり工法):1箇所46,000円~266,000円
- ドア交換(カバー工法):1箇所43,000円~266,000円
- ドア交換(はつり工法):1箇所46,000円~266,000円
- 上記の合計が支給。限度額は1戸あたり200万円
2023年版の制度に比べて、ほとんどの工事で補助金額がアップしているほか、新たにドア交換も補助金の対象となった点に違いがあります。
支給条件
リフォームで「先進的窓リノベ2024事業」の補助金を受け取るための条件は、大きく分けて以下の3つです。
- 補助金額が5万円以上であること
- 使用する窓やガラスは規定されている製品のなかから選ぶこと
- 制度の登録事業者がリフォームを請け負うこと
申請方法
先進的窓リノベ2024事業の申請手続きは施工業者が行います。そのため、施主(リフォームの発注者)は直接申請作業を行うことはありません。
施主が行うことは「業者とのやりとり」「工事費用の支払い」の2つのみです。
ただし、申請の代行が可能な業者は本事業の登録業者のみとなっています。登録業者は公式サイトの「補助金利用を相談できる事業者の検索」から行えます。
申請時に業者と国の間でおこなうやりとりは以下のようになっています。
- [住宅所有者・業者]工事請負契約の締結
- [業者]着工~完了
- [業者]補助金交付申請
- 【国】審査・補助金交付決定
- [業者]完了報告・補助金の請求
- 【国】完了報告の確認
- 【国】補助金の振込
■問い合わせ窓口
・窓口:住宅省エネ2024キャンペーン 補助事業合同お問い合わせ窓口
・電話番号:0570-055-224(ナビダイヤル)、03-6625-2874(IP電話等からの場合)
※受付時間 9:00~17:00(土日祝含む)
・公式サイト:住宅省エネ2024キャンペーン 補助事業合同お問い合わせ窓口
現在の募集状況(2024/03/06更新)
本制度は受付開始前です。交付申請期間は2024年3月中下旬 ~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)となっています。
最新の情報は、子育てエコホーム支援事業の公式サイトをご確認ください。
③給湯省エネ2024事業
「給湯省エネ2024事業」とは、指定の高効率給湯器を自宅に導入する場合に補助金が受け取れる制度です。
制度の重要ポイント
- 対象機器はエネファーム・ハイブリッド給湯器・エコキュートの3種類
- 補助金額はエネファームが1台18万円、ハイブリッド給湯器が1台10万円、エコキュートは1台8万円
- 制度の登録事業者が工事を請け負う必要あり
補助金額
「給湯省エネ2024事業」で受け取れる補助金額は以下のとおりです。
- 家庭用燃料電池(エネファーム)が1台あたり18万円
- 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)は1台あたり10万円
- ヒートポンプ給湯機(エコキュート)は1台あたり8万円
- 戸建住宅の場合はいずれか2台分まで、マンション等は1台分まで申請可能
支給条件
「給湯省エネ2024事業」の支給条件は大きくわけて以下の3つです。
制度の登録リストにある機器を使用することリフォーム工事は制度の登録事業者が請け負うこと
申請者は、住宅の所有者またはその家族等であること
[/box]
申請手順
給湯省エネ2024事業の申請手続きは、工事を請け負った施工業者が行います。そのため、住宅の所有者が直接行う手順はありません。
申請代行が可能な登録事業者は、制度公式サイトの「補助金利用を相談できる事業者の検索」から行えます。
■問い合わせ窓口
・窓口:住宅省エネ2024キャンペーン 補助事業合同お問い合わせ窓口
・電話番号:0570-055-224(ナビダイヤル)、03-6625-2874(IP電話等からの場合)
※受付時間 9:00~17:00(土日祝含む)
・公式サイト:住宅省エネ2024キャンペーン 補助事業合同お問い合わせ窓口
現在の募集状況(2024/03/06更新)
本制度は受付開始前です。交付申請期間は2024年3月中下旬 ~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)となっています。
最新の情報は、子育てエコホーム支援事業の公式サイトをご確認ください。
④賃貸集合給湯省エネ2024事業

「賃貸集合給湯省エネ2024事業」は、賃貸住宅や集合住宅の給湯器をエコジョーズかエコフィールに交換した場合に補助金が受け取れる制度です。
申請者は、賃貸住宅などのオーナーや管理法人に限られます。
制度の重要ポイント
- 対象機器は「エコジョーズ」と「エコフィール」の2種類
- 補助金額は追い焚き機能のある機器が1台7万円、無いものが1台5万円
- 制度の登録事業者がリフォームを請け負う必要あり
補助金額
「賃貸集合給湯省エネ2024事業」をリフォームで申請した場合の補助金額は、1台あたり5万円もしくは7万円です。
金額は、導入する給湯器に追い焚き機能があるかどうかによって変わります。
- 追い焚き機能があるエコジョーズ・エコフィール:1台あたり7万円
- 追い焚き機能がないエコジョーズ・エコフィール:1台あたり5万円
上限の金額が、集合住宅の1住戸あたり1台を上限に補助されます。
支給条件
「賃貸集合給湯省エネ2024事業」をリフォームで申請した場合の支給条件は大きくわけて以下の4つです。
- 1棟あたり2戸以上の給湯器を交換すること
- 制度の登録リストにある機器を使用すること
- 申請者は賃貸集合住宅のオーナーまたは管理法人等であること
- リフォーム工事は制度の登録事業者が請け負うこと など
性能要件
エコジョーズ・エコフィールともに一定の熱効率を満たす必要があります。
詳しくは公式サイトをご覧ください。
対象製品
対象となる給湯器のメーカーと型番は、制度公式サイトの「補助対象製品の検索」から確認できます。
申請手順
賃貸集合給湯省エネ2024事業の申請手続きは、工事を請け負った施工業者が行います。
制度公式サイトの「補助金利用を相談できる事業者の検索」から、本制度の登録事業者の確認が可能です。
■問い合わせ窓口
・窓口:住宅省エネ2024キャンペーン 補助事業合同お問い合わせ窓口
・電話番号:0570-055-224(ナビダイヤル)、03-6625-2874(IP電話等からの場合)
※受付時間 9:00~17:00(土日祝含む)
・公式サイト:住宅省エネ2024キャンペーン 補助事業合同お問い合わせ窓口
現在の募集状況(2024/03/06更新)
本制度は受付開始前です。受付開始は、2024年3月中下旬以降を予定しています。
最新の情報は賃貸集合給湯省エネ2024事業の公式サイトからご確認いただけます。
⑤長期優良住宅化推進事業
「長期優良住宅化リフォーム推進事業」は、国の補助金制度のなかでも対象工事が幅広い制度です。
具体的には、建物の劣化対策や耐震性向上、省エネ対策、三世代同居のための増築や、子育て対応改修などが対象となっています。
制度の重要ポイント
- 補助金額は施工費用の3分の1程度(上限100万円~250万円)
- 対象工事は耐震性・省エネ性などの向上、三世代同居対応、子育て環境整備[/text]など幅広い
- 工事後は一定の耐震性・劣化対策・省エネルギー性が確保されていることが必要
補助金額
「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の補助金額は以下のとおりです。申請額はおおむね費用の3分の1で、申請区分によって上限額が代わります。
- 「評価基準型」:施工費用の3分の1(上限100~150万円)
- 「認定長期優良住宅型」:施工費用の3分の1(上限200万円~250万円)
リフォーム後の住宅性能によって「評価基準型」「認定長期優良住宅型」のいずれかが適用され、補助金額が決まります。
上限額は、「長期優良住宅認定をとるか」「三世代同居化の工事をするか」「若者・子育て世帯であるか」によって変動します。これらに当てはまる場合は、支給上限額が50万円加算されます。
支給条件
長期優良住宅化リフォーム推進事業の補助金を受けるためには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- リフォーム工事前にインスペクション(住宅性能評価)を行うこと
- リフォーム工事後の建物が、劣化対策、耐震性、省エネルギー対策の性能基準を満たすこと
- 前項を満たす「性能向上リフォーム」「三世代同居対応改修」「子育て世帯向け改修」「防災性・レジリエンス性向上改修」のうち、1つ以上の工事を行うこと
補助金の対象となるリフォームには以下の11種類があります。
- 省エネ性の向上(高断熱化、エコ機器の設置など)
- 耐震性の向上(壁の強化、屋根の軽量化など)
- 構造の長寿命化(防腐・防蟻処理、ユニットバスへの交換など)
- 設備の維持更新(給排水管の更新など)
- バリアフリー化(手すりの設置、床の段差解消など)
- 外装等の修繕・補修(外壁塗装、屋根の葺き替え、雨樋交換など)
- テレワーク環境整備(部屋の間仕切り設置など)
- 高齢期への備え(玄関の拡大、未使用部屋の別用途化など)
- 三世代同居対応(水回り設備の増設など)
- 若者・子育て世帯が実施する改修(床のクッション化、対面キッチンへの変更など)
- 防災性の向上(地震、台風、水害への備えなど)
申請方法
「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の補助金申請は、居住者ではなくリフォーム会社が行います。
ただし、申請を行えるのは制度に登録された施工業者のみのため、増築にあたっては登録されている業者を選びましょう。
長期優良住宅化リフォーム推進事業に登録されている個人・法人は、公式サイトの「令和5年度 長期優良住宅化リフォーム推進事業」から行うことができます。
また、補助業者申請手順は以下のとおりです。
- [業者]インスペクションの実施
- [業者]リフォーム・増築内容の決定
- [業者]住宅登録
- [業者]交付申請手続き
- 【事務局】交付決定通知
- [業者]増改工事の実施
- [業者]完了報告手続き
- 【事務局】現地検査
- 【事務局】交付額確定通知
- 【事務局】補助金の支払い
■問い合わせ窓口
・窓口:国立研究開発法人 建築研究所 長期優良住宅化リフォーム推進事業評価室
・電話番号:03-5805-0522
※平日 10:00~16:00(12:00~13:00除く)
・公式サイト:https://www.kenken.go.jp/chouki_r/
現在の募集状況(2024/03/06更新)
現在は受付停止中です。令和5年度の交付申請は「認定長期優良住宅型」「評価基準型」ともに2024年2月29日をもって終了しました。
令和6年度の補助金の有無や募集期間については未発表です。
最新の募集状況は制度公式ページでご確認ください。
⑥断熱リフォーム支援事業
「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」は、戸建住宅や集合住宅の窓・床・天井・外壁などの断熱リフォームをした際に受け取れる補助金です。
制度の重要ポイント
- 補助金額は改修費用の3分の1(上限15万円~120万円)
- 断熱リフォーム(天井・床・窓・外壁)や家庭用蓄電システムの設置などが補助の対象
- 9月期の募集を2023年9月4日から受付中
補助金額
「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」の補助金の支給額は以下の通りです。支給額は「工事の種類」と「住宅の種類」によって決まります。
- 建物の断熱改修:施工費用の3分の1(上限:戸建120万円、集合住宅15万円)
- 省エネ機器の導入:施工費用の3分の1(上限:1機器につき5万円~20万円)
- 照明のLED化:施工費用の3分の1(上限:1箇所あたり8,000円。集合住宅共用部のみ)
いずれの工事も支給額は施工費用の3分の1であるのが特徴です。
支給条件
「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」で補助金を受けられるのは、15%以上の省エネ効果が見込まれる断熱リフォーム(トータル断熱)もしくは高断熱な窓を使用した居間の断熱改修のどちらかです。
また、補助対象となる建物は住宅のみで、店舗や事務所との併用物件は対象外となります。
- 規定以上の断熱効果が見込まれる建材を使うこと
- 補助金の交付決定後に契約・着工すること
- 工事に使う建材や省エネ設備は定められた製品から選ぶこと
- 住居専用の建物であること
補助対象製品は、制度公式サイトの「補助対象となる製品|断熱リフォーム支援事業」から確認できます。
申請方法
「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」の申請手順は以下のとおりです。
- 【施主】増築・リフォームの見積もりを取得し、依頼先を決める
- 【施主】運営団体の「HECO」へ書類をメールと郵送で提出
- [国]が書類を審査・交付決定通知書を送付
- 【施主】増改築の工事・完了
- 【施主】施工業者へ支払い
- 【施主】完了実績を提出
- [国]審査・交付額の決定通知
- 【施主】請求書を提出
- [国]補助金の振込み
申請者から補助金運営団体への書類提出が3回発生するのが特徴です。
■問い合わせ窓口
・窓口:(公財)北海道環境財団 補助事業部
・電話番号:011-206-1573
※受付時間 10 :00~17:00(平日のみ)
・公式サイト:https://www.heco-hojo.jp/danref/index.html/
現在の募集状況(2024/03/06更新)
現在、令和6年1月次の申請を受付中です。公募期間は令和6年1月24日(水)~令和6年3月1日(金)となっています。
本制度は年4回(1月次・3月次・6月次・9月次)の公募を行うことが通例となっています。最新の受付状況は公益財団法人北海道環境財団の公式ホームページを随時チェックしてください。
⑦各市区町村の補助金制度
国(省庁)が運営する補助金とは別に、お住まいの都道府県や市区町村がリフォーム工事を対象とした補助金を設置している場合があります。
補助金額
補助金額を、制度のパターンごとに解説します。
市民向けパターン
増改築費用の5%~20%程度を支給。上限額は多くは5~10万円。高くても20万円程度を限度額としている制度が多いです。
バリアフリー化パターン
増改築費用の50%~100%(満額)を支給。支給上限額は10万円程度のところから100万円近くまで幅があります。
移住者・定住者パターン
増改築費用の30%~50%が多い。支給上限額は30万円ほどの自治体から、100万円以上のところもあります。
多世代同居パターン
多くは増改築費用の50%~100%(満額)を支給。支給上限額は30万円~50万円ほどの自治体が多いようです。
支給条件
支給条件は自治体や制度によりさまざまですが、よくある条件としては以下のようなものがあります。
市民向けパターン
自己居住用の市内住宅を、市内業者が請け負って施工する場合が対象のパターン。増改築に限らず、幅広い住宅工事が対象なことが多いです。
- 市町村内にある自己居住用の住宅の増築であること
- その市町村に住民票をおいていること
- 市町村内の業者を利用すること など
バリアフリー化パターン
高齢者などが居住する住宅をバリアフリー化する場合に補助金対象となるパターン。増改築の場合は、風呂・トイレ・廊下・階段などの拡張や、生活しやすい居室の増設などが当てはまるでしょう。
- 高齢者、要介護者、障がい者等が居住している住宅であること
- 介護保険の住宅改修補助を先に使うこと
- 介護保険の制度では非該当となったこと など
移住者・定住者パターン
市内の中古住などを取得し、住み始めるために増改築する場合に補助金が支給されるパターン。新たに取得した住宅である必要がない場合もあります。
- Uターン者・Iターン者などであること
- 一定年数(3~10年)以上の定住を誓約すること
- 空き家バンクを通して物件を入手しているこ など
多世代同居パターン
親・子世代が新しくに同居するための増改築費用が補助されるパターン。市内にいずれかの世帯が先に住んでいる必要がある制度がほとんどです。
- 新たに多世代同居(親・子・孫)をはじめること
- キッチン、浴室、トイレ、玄関のうち、1か所以上の増築または改修を行うこと
- 子世帯には中学生以下の子どもがいること など
申請手順
自治体の役所・役場の産業振興課か住宅政策課、福祉課などが窓口になっている制度が多いです。
多くの制度では増築工事の契約や着工より前の申請を条件としているところが多いため、気をつけましょう。
制度の探し方
地方自治体の設置する補助金制度は、以下の方法で探すことができます。
- 役所のサイトを「補助金」「助成金」などで検索
- 役所のサイトの「住宅」「くらし」「住まい」などのカテゴリから補助制度を探す
- 住宅リフォーム推進協議会の「支援制度検索サイト」で都道府県を指定し検索
⑧介護保険制度
「介護保険における住宅改修」とは、介護をしやすくするための住宅改修をした場合に費用の補助が受けられる制度です。
申請先は各自治体で、受付は年間を通して随時行われています。
制度の重要ポイント
- 補助金額は施工費用の90%(上限18万円)
- 住宅に要介護・要支援指定を受けている人が住んでいる必要あり
- 増築費全体ではなく、手すり取付けや風呂トイレの改修等の費用を基準に支給
補助金額
「介護保険における住宅改修」の補助金の上限額は以下のとおりです。
- 改修費用の90%(上限18万円)
ただし、所得が高い場合は補助金額が費用の「80%」もしくは「70%」(上限額はそれぞれ16・14万円)に下がる場合もあります。
支給条件
「介護保険における住宅改修」の補助金を受けるためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 介護保険の被保険者が要支援・要介護認定を受けている
- 介護保険の被保険者が自宅で生活している
- 工事地が「介護保険被保険者証」に記載されている自宅住所である
また、補助を受けられる工事内容は「介護を円滑に行うための改修」か「要支援・要介護者が安全に暮らしやすくするための改修」に限られます。
具体的には以下の6つのいずれかに当てはまる必要があります。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
そのため、増築にかけた費用全体が対象となるわけではなく、増改築費用のうち上記に当てはまる金額の90%が18万円を限度に支給されることになります。
引用:厚生労働省「介護保険における住宅改修」
申請方法
増築工事に「介護保険における住宅改修」の申請手順は以下のとおりです。まずは要支援・要介護者の担当のケアマネジャーに相談を行いましょう。
また、給付方法は償還払いとなっているため、一度リフォーム会社に費用の全額を支払い、後日自治体から補助金の給付を受ける流れとなります。
- 住宅改修についてケアマネジャー等に相談
- 申請書類又は書類の一部を市町村へ提出
- 市町村が確認・審査
- 増築工事の施工・完成
- 工事終了後、書類を市町村へ提出し支給申請
- 市町村が確認・支給認定
- 住宅改修費の支給
■問い合わせ窓口
・窓口:市区町村の役場にある介護保険の担当課、地域包括支援センター等
・電話番号:市町村による
住宅改修概要資料(厚生労働省)
現在の募集状況(2024/03/06更新)
年間を通して随時受付中です。
補助金制度を利用したい場合は、担当のケアマネジャーや役場の介護保険担当課へご相談ください。
リフォーム工事別・対象補助金の早見表
「住宅の部位」と「よくあるリフォーム工事の内容」に対応した、補助金が下りる可能性がある制度は以下の表のとおりです。
なお、補助金の支給には工事金額や他の工事との組み合わせなどの条件を別途満たす必要がある場合があります。
表内の各制度名を押下すると、支給額や条件等の解説箇所へジャンプします。
「キッチン」のリフォーム
| リフォーム内容 | 申請可能な補助金 |
|---|---|
| 食洗機の導入 | ・子育てエコホーム支援事業 |
| 掃除しやすい レンジフード |
・子育てエコホーム支援事業 |
| 節湯水栓の導入 | ・子育てエコホーム支援事業 |
| ビルトイン 自動調理対応コンロ |
・子育てエコホーム支援事業 |
| 対面キッチン化 | ・子育てエコホーム支援事業 |
| キッチンの増設 | ・子育てエコホーム支援事業 |
「お風呂」のリフォーム
| リフォーム内容 | 申請可能な補助金 |
|---|---|
| 高断熱浴槽の導入 | ・子育てエコホーム支援事業 |
| 浴室乾燥機の設置 | ・子育てエコホーム支援事業 |
| お風呂の増設 | ・子育てエコホーム支援事業 |
| 在来浴室のユニットバス化 | ・長期優良住宅化推進事業 |
「トイレ」のリフォーム
| リフォーム内容 | 申請可能な補助金 |
|---|---|
| 節水型トイレの導入 | ・子育てエコホーム支援事業 |
| トイレの増設 | ・子育てエコホーム支援事業 |
「洗面台」のリフォーム
| リフォーム内容 | 申請可能な補助金 |
|---|---|
| バリアフリー化 |
・長期優良住宅化推進事業 ・子育てエコホーム支援事業 |
屋根・外壁のリフォーム
| リフォーム内容 | 申請可能な補助金 |
|---|---|
| 外壁・屋根の断熱材追加 |
・断熱リフォーム支援事業 ・子育てエコホーム支援事業 |
| 屋根の軽量化 | ・長期優良住宅化推進事業 |
| 外壁・屋根の塗装 | ・各市区町村の補助金制度 |
「床・壁・天井」のリフォーム
| リフォーム内容 | 申請可能な補助金 |
|---|---|
| 天井・床の断熱材追加 |
・断熱リフォーム支援事業 ・子育てエコホーム支援事業 |
| 床の段差解消 |
・長期優良住宅化推進事業 ・子育てエコホーム支援事業 ・介護保険制度 |
「窓・玄関・開口部」のリフォーム
| リフォーム内容 | 申請可能な補助金 |
|---|---|
| 窓ガラス交換 |
・子育てエコホーム支援事業 ・先進的窓リノベ2024事業 |
|
内窓の設置 (二重窓化) |
・断熱リフォーム支援事業 ・子育てエコホーム支援事業 ・先進的窓リノベ |
| 外窓の交換 |
・断熱リフォーム支援事業 ・子育てエコホーム支援事業 ・先進的窓リノベ |
| 玄関ドア交換 |
・断熱リフォーム支援事業 ・子育てエコホーム支援事業 |
| 玄関の増設 | ・子育てエコホーム支援事業 |
| 防犯性の高い窓・ドアへの交換 |
・長期優良住宅化推進事業 ・子育てエコホーム支援事業 ・介護保険制度 |
「給湯器」の入れ替え
| リフォーム内容 | 申請可能な補助金 |
|---|---|
| 高効率給湯器の導入 |
・子育てエコホーム支援事業 ・給湯省エネ2024事業 ・賃貸集合給湯省エネ2024事業 |
その他のリフォーム
| リフォーム内容 | 申請可能な補助金 |
|---|---|
| 再エネ・創エネ設備の導入 |
・子育てエコホーム支援事業 ・各市区町村の補助金制度(エコ制度) |
| 宅配ボックスの設置 | ・子育てエコホーム支援事業 |
| 手すりの設置 |
・長期優良住宅化推進事業 ・子育てエコホーム支援事業 ・介護保険制度 |
| 雨水タンクの設置 | ・長期優良住宅化推進事業 |
| 床下の防腐・防蟻処理 | ・長期優良住宅化推進事業 |
| テレワーク対応化 | ・長期優良住宅化推進事業 |
まとめ:補助金申請と同時に「相見積もり」も忘れない

リフォーム工事をなるべくお得にしたい場合、補助金の利用がおすすめです。
加えてそれだけでなく、施工金額自体を下げることも考えるべきです。
その際に有効なのが相見積もりです。
相見積もりをせずにリフォーム工事を契約したために、金額面で損をしたりあとから後悔する方がとても多いのです。
相見積もりの効果
工事を契約する前に、最低3~4社以上からは見積もりをとって内容や金額を比べることで、対応がしっかりしていて価格もリーズナブルな業者に出会える確率が高まります。
また補助金の申請通過には、予定している施工費用が適正な範囲かどうかも問われると思われますので、書類審査を通るためにも相見積もりは重要です。
相見積もり先の心当たりがない場合
「見積もり先の業者にそんな心当たりがない…」という場合は、全国の優良業者のデータをもつ無料の相談窓口
にお気軽にご相談ください。
画面に沿っていくつかの回答を選ぶだけで、あなたのリフォームの適正金額や対応可能な業者を回答します。
- 建築工事研究会『積算資料ポケット版 リフォーム編 2022年度版』一般社団法人経済調査会 2021
- 田村誠邦・甲田珠子『プロのための住宅・不動産の新常識』エクスナレッジ 2019
- 菊池克弘『住宅リフォーム重要事項32選』都市環境建設 2015