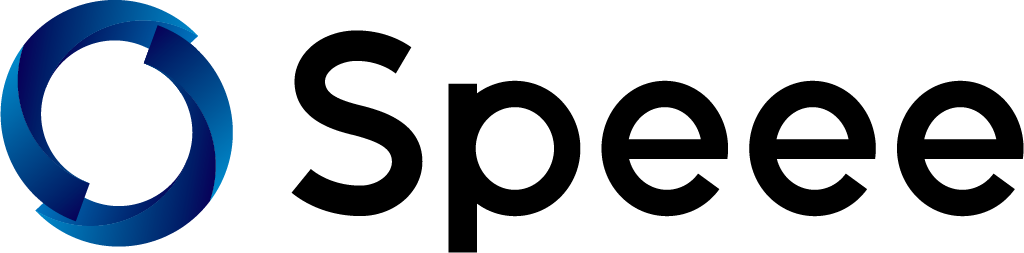外壁の塗装方法には、吹き付け工法とローラー工法の2種類があります。
近年の外壁の塗り替えではローラー工法が主流になっていますが、モルタル壁の場合は現在も吹き付け工法が採用されています。
この記事では、「吹き付け塗装とはなにか」「吹付け塗装のメリット・デメリット」「吹付け塗装とローラー塗装の違い」などを解説します。
吹き付け塗装とは?
吹き付け塗装とは、スプレーガンを使用して塗料を霧状にして壁面に吹き付ける工法のことです。吹付け塗装は、主にモルタルの外壁に意匠性の高い仕上げを行う際に使用されます。
具体的には、「リシン吹き付け」「スタッコ仕上げ」「吹付けタイル仕上げ」などの仕上げの際に用いられています。
【吹き付け塗装の例】

なお現在では、戸建ての塗装においては吹付け塗装よりもローラー塗装が行われることが多くなっています。
これは、「サイディングボードなど、最初からデザインがつけられている外壁材を使用する家が増えたこと」「吹付け塗装では飛沫が周囲に飛散しやすいというデメリットがある」という2点が主な理由です。
吹き付け塗装に用いられるスプレーガンは2種類
吹き付け工法に使用されるスプレーガンには「エアスプレー」と「エアレススプレー」の2種類があり、以下のような違いがあります。
エアスプレー
エアスプレーは、圧縮した空気を利用し塗料をミスト状にして噴射するスプレーガンです。
エアスプレーの中でも、重力式・吸上式・圧送式の3種類に分類することができます。
エアスプレーは細かな調整ができるため、塗装面がきれいに仕上がることがメリットです。
一方デメリットは、塗料が飛散しやすいことや、塗膜が薄くなりやすいことです。
エアスプレーは、石材調やタイル吹き・スタッコ・リシンなど吹き付けでなければ出せないテクスチャのときに使用するのが一般的です。
エアレススプレー
エアレススプレーは、空気を利用するのではなく、塗料に直接圧力をかけることで噴射口から飛ばす仕組みのスプレーガンです。
エアレススプレーは、粘度の高い塗料にも使用でき、塗料の無駄が少ないことがメリットです。
ただし、細かな部分の塗装には不向きというデメリットもあるので注意してください。
吹き付け塗装のメリット・デメリット
吹き付け塗装の概要が分かったところで、次はもう少し詳しく特徴を見ていきましょう。
吹き付け塗装のメリットとデメリットには、以下のようなものがあります。
吹き付け塗装のメリット
まずは、吹き付け塗装のメリットを見ていきましょう。
吹き付け塗装のメリットは3つあります。
メリット①施工にかかる時間が短い
吹き付け塗装は、スプレーガンを使用することで一度に広範囲を塗装することができます。
そのため、工場や倉庫などの広範囲の塗装でも、短時間で効率的な施工が可能です。
メリット②凹凸のある立体感のある模様を表現できる
飛沫で塗装する吹き付け塗装は、凹凸のある外壁にもムラなく塗装をすることができるというメリットがあります。
ローラーでの塗装は凹凸の間の隙間をうまく塗れないことも多いので、でこぼことした複雑な表面の外壁には、吹き付け塗装が向くでしょう。
メリット③低コスト
吹き付け塗装は施工にかかる時間が短く、塗装に携わる人員が少なくすむため、人件費を削減できます。
飛沫が飛びやすいので養生には手間がかかりますが、一般的にはローラー工法より低コストになります。
吹き付け塗装のデメリット
次に、吹き付け塗装のデメリットを確認しましょう。
吹き付け塗装には、主に4つのデメリットがあります。
デメリット①塗料が周辺に飛散しやすく、近所迷惑になる可能性がある
吹き付け塗装はスプレーガンで塗料を霧状にするので、養生をしていても塗料が近所に飛散しやすいというデメリットがあります。
近所の家や車を汚してしまう可能性があるので、住宅が密集している地域は吹き付け塗装に向きません。
デメリット②使用する塗料の量が多い
吹き付け塗装は周辺への塗料の飛散が多いので、同じ面積でもローラーより多くの塗料が必要になります。
一般的には、吹き付け塗装はローラーでの塗装に比べて3割ほど多く塗料が必要と言われています。
デメリット③塗装時に騒音が発生する
吹き付け塗装でスプレーガンを使用する際、コンプレッサーという機械が必要です。
このコンプレッサーの機械音が騒音と感じる人もいるため、近隣に配慮する必要があります。
デメリット④対応できる職人の数が減りつつある
先述のように、現在戸建ての塗装はローラーで行われるのが主流です。
そのため、吹き付け塗装ができる職人は、年々少なくなっています。
もちろん経験が浅くても吹き付けで塗装することは可能ですが、ムラになりやすいので、吹き付け塗装を頼むときは、職人に吹き付け塗装の経験があるかを確認しておくのがよいでしょう。
ローラーと吹き付けのどちらで塗装すべき?

さて、ローラーでの塗装と吹き付け塗装のどちらかを選択する場合は、どうしたらいいのでしょうか?
工法上、どうしても塗料の飛散があるため、住宅が多く密集する地域での施工は避けられがちになっています。
住宅の外壁の場合は、「どうしても吹き付け塗装でしか表現できない模様を付けたい」という場合を除き、ローラー工法を選択しましょう。
ローラー工法は吹き付け工法より模様の多様性に劣ることや、乾燥が遅い(塗膜が厚くなるため)などのデメリットはあります。
しかし、一般的なサイディング外壁の塗装にはあまり必要性がありません。先ほども紹介しましたが、現在はローラー工法が主流です。
住宅密集地域での吹き付け塗装は、クレームが発生しやすいことなどから、ローラー工法しか取り扱っていないという塗装業者もあります。
ローラー工法は吹き付け工法と違って、塗料の無駄がない・騒音が発生しないというだけでなく、仕上がりの塗膜が厚くなるため耐久性にも優れます。
吹き付け塗装の仕上げ例
最後に、吹き付け工法の代表的な仕上げ例をご紹介します。
以下の外壁は、ローラー塗装ではなく吹き付け塗装で仕上げることが多い外壁です。
凹凸の目立つデザインが多いことが共通の特徴として挙げられます。
スタッコ仕上げ

スタッコ仕上げとは、外壁にモルタルや合成樹脂を塗り付けた後、セメント・塗料・骨材などを混ぜた仕上げ材を厚く(5~10mm程度)吹き付ける仕上げ方法です。
さらに、そのまま乾燥させる「吹き出し仕上げ」(吹きっぱなし仕上げともいう)と吹き付けた後にローラーで押さえる「凸部処理仕上げ」があります。
意匠性が高く重厚感のある仕上げになりますが、凹凸があるため汚れが溜まりやすいのがデメリットです。
吹き付けリシン仕上げ

吹き付けリシン仕上げは、モルタル壁の最も一般的な仕上げ方法で、古くから普及しています。
塗料に砂壁状の骨材を混ぜた仕上げ材をリシンガンで吹き付けて仕上げます。
スタッコ仕上げとの違いは塗膜の厚みです。スタッコ仕上げは厚い塗膜になりますが、リシン仕上げは塗膜が薄くなります。
リシン仕上げは、施工が早いことや比較的低コストで施工できることがメリットです。
デメリットは、塗膜が薄いため、クラックが発生しやすく耐久性が低いことです。
しかし近年では、クラックに強い弾性リシンも普及しています。
リシン掻き落とし仕上げ

引用:http://www.nissaren.or.jp/455
リシン掻き落としは、吹き付けリシン仕上げにさらに1工程加え、凹凸を細かくした仕上げです。
リシンを吹き付けたあと、ブラシなどで表面を削ってなだらかにします。
リシン掻き落としは上品な印象の外壁になる一方、凹凸が細かいためにリシン吹き付け以上に汚れが溜まりやすいというデメリットもあります。
吹き付けタイル仕上げ

吹き付けタイル仕上げは、その名称からタイル工事と混同されがちですが、外壁塗装の吹き付け仕上げの一種です。ボンタイルや玉吹き塗装と呼ばれることもあります。
画像は、吹き付けタイルのヘッドカット仕様になります。
リシン仕上げやスタッコ仕上げは吹き付けた段階で仕上がりとなるのに対し、タイル仕上げは下地調整材(タイルベース)を専用ガンで飛ばし玉状の模様を付けた後、さらに仕上げ材を被せるため、複層仕上げ(4~5工程)になることが他の仕上げと異なる点です。
吹き付けタイル仕上げは玉状の模様を付けるため塗膜が厚く、クラックが目立ちにくいなどのメリットがあります。
耐久性は上塗り塗料の種類によって左右されます(シリコン塗料やフッ素塗料なら耐久性が高い)。
デメリットは、凹凸をきれいに表現できるかは、職人の腕によって違ってくることです。
まとめ
外壁塗装を実施する際は、塗装業者に見積書をもらった後にチェックするポイントが多くありますが、施工方法についても明確にしてもらいましょう。
見積書に工法まで記載されていない場合、直接口頭で聞くことをオススメします。
吹き付け塗装かローラー工法かで、同じ塗料を使用しても耐久性が異なり、次回の塗装サイクルも違ってきます。
また、隣家と近い場合はトラブル回避のためにもやはりローラー工法がオススメです。
こちらの記事をふまえたうえで、塗装の効果と必要性について詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。
>>「塗装はなぜ必要?効果・種類・費用や業者の選び方をやさしく解説」